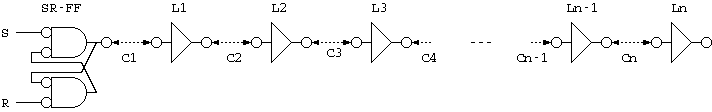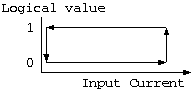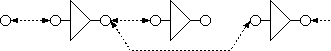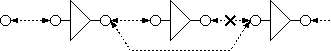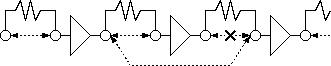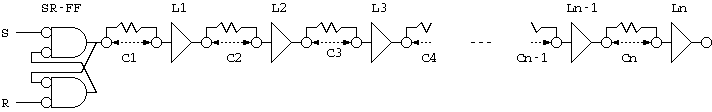点滅のタイミングやパターンの変化から
多様な異常に気づくのがこのアナログ的デジタル回路の利点です。
3. 特殊な配線と不良パターンへの対応
試料に分岐がなければ、以上で十分ですが、
分岐がある場合は、図3のように接続します。
この場合も、2 つの遅延素子が同時に論理反転するため、
オペレータは分岐があることを視覚的に確認することができます。
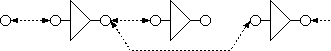
図3 - 分岐のある試料への対応
ところが、これをやると新たな問題が発生します。
図4の分岐のあるケースで断線と短絡が同時に発生すると、
不良でありながら発振が止まらない場合があるのです。
発振の周期とタイミングの違いで「変だな」と気が付く可能性もありますが、
不良を見逃す可能性大です。
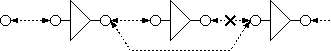
図4 - 基本回路のままでは不良判定が難しいケース
しかし、この問題には遅延素子のヒステリシスを活かした
スマートな解決策があります。
試料導体が断線していれば前段の遅延素子の出力が 1 になっても
後続遅延素子の論理が 0 から 1 にならず、
試料導体が導通していて前段の遅延素子の出力が 0 になっても
後続遅遅延素子の論理が 1 から 0 に戻らないような高抵抗を
すべての試料接続端子間に付加するのです。
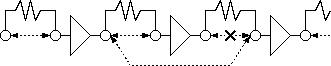
図5 - 抵抗だけで難問解決
遅延素子の論理が 0 から 1 に変わるときは、
この抵抗を流れる電流が後続の遅延素子の論理を 1 にすることができず、
抵抗の低い試料導体が必要ですが、
遅延素子の論理が一旦 1 になると、
この抵抗が断線した試料に代わって断線試料直前の遅延素子の論理を 1 に保持します。
こうして、遅延素子のヒステリシスは、
導通検査と絶縁抵抗検査に加えて、
特殊な分岐パターンの断線・短絡(絶縁)同時不良対策という
2つの役割を果たすことになります。
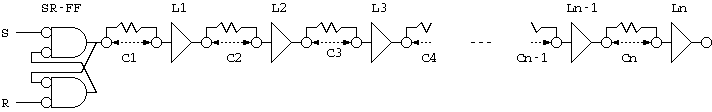
図6 - 最終的な回路 (SR-FF の S, R 信号生成回路を省略)
かつて、最終的な導通検査回路は図6のようになりました。
4. 実用的な試験装置の設計
実用的な試験装置を作る場合は、
- 多様な導体数への対応
- 多様な分岐回路への対応
が必要ですが、
試験導体の最大数に対応できる遅延素子を用意して、
導体が少ないときは、
試験治具(jig)のダミー導体などで不足導体を補えば、
容易に汎用性を持たせることができます。
私の場合は当時、小型マイクロフォンに使われる 2 極の
2.5 mm フォーンプラグを使いました。
このジャックはプラグを差さないとき自動的に短絡されますので、
治具のダミー導体を省略できます。
もちろん、試験導体の数が多いときは、高密度コネクタで治具との接続を行い、
治具側にダミー導体を用意するほうが有利です。
導体抵抗と絶縁抵抗の両方が判定できるような入力ヒステリシスを持つ遅延素子の実現
にもいろいろな方法がありますが、
私が最初にこれを作った昭和 40 年代には、
2a+2b 接点を持つ超小型リード・リレーとダーリントン接続トランジスタの組み合わせを
使いました。リレーの接点は 4a でも作れますし、
今なら半導体だけでもできます。
5. 注
5.1. 注1 - 導通検査
導通検査は、電気が通るべきところに通り、
通るべきでないところに通らないことを確認するわけですが、
通るか通らないかの判定には、
多くの規格がランプの点灯やブザーの鳴動を使う手法を採用しています。
こういった曖昧な検査が実用になる理由は、
組み立て前の部品段階の検査として、
構造、耐電圧、絶縁抵抗試験等の検査が行われているためです。
5.2. 注2 - 絶縁抵抗試験
絶縁抵抗試験は比較的高電圧の微小電流測定になりますから、
装置も複雑で測定時間も長くなります。
従って、通常の導通検査では考慮しないのですが、
モールドコネクタなどの場合は、
成形前の下加工や成形時の熔融樹脂や圧力によって、
短絡まではゆかない絶縁低下を生ずることがあって、
できれば採用したい検査の1つです。
耐電圧試験になると、もっと大事で、感電の危険も大きいですから、
よほどの場合以外は部品レベルで実施しておきます。
なお、耐電圧試験もその根拠は曖昧で、
長年うまく機能してきたからというのが根拠(言い訳)になっています。
5.1. 注3 - 特許 昭 54-12764
この発明の特許権は既に消滅しています。
文系の弁理士さんが作成した特許広報は私には理解できません。
他のほとんどの特許がそうですが。
平林 浩一, 2012-12